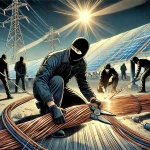高速バスの座席予約で起きる「相席ブロック」:キャンセル料とマナー
「性善説に訴えるのは限界」JRバスの警告も完全無視…「相席ブロック」問題を呼びかけも効果はナシ | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
高速バスの座席予約システムで、「相席ブロック」と呼ばれる迷惑行為が全国のバス会社で増加している。今年のゴールデンウィーク前には、JRバス関東が公式Xで行為をやめるよう呼びかけ、話題になった。
みなさんは高速バスの座席予約をしたことがありますか?最近、「相席ブロック」という迷惑行為が全国のバス会社で問題になっています。なぜこのような行動が増えているのでしょうか?また、どうして高速バスのキャンセル料は他の交通機関に比べて安いのでしょうか?
「相席ブロック」問題の仕組みや背景、今後の対策について、そして公共交通のマナーやルールについて考えてみましょう。
「相席ブロック」とは何か?
予約システムの悪用
「相席ブロック」とは、一人で隣り合う2つの座席を予約し、出発直前に1席だけキャンセルする行為です。この方法を使うと、隣の席が空いたままになり、他の人はその席を利用できません。実際には空席があるのに「満席」と表示されてしまい、本当にバスに乗りたい人が予約できなくなります。
どんな影響があるのか
この行為は、バス会社にとって大きな損失です。売上が減るだけでなく、混雑する時期には多くの人が困ってしまいます。SNSでも「本当に乗りたい人が乗れなくなるのは困る」という声が多く上がっています。
なぜ「相席ブロック」が増えているのか?
キャンセル料の安さが原因
「相席ブロック」が広がった理由のひとつは、キャンセル料がとても安いことです。多くのバス会社では、出発直前でもキャンセル料が110円程度しかかかりません。そのため、2席予約してもほとんど損をせずに隣の席を空けておくことができてしまいます。
キャンセル料が安い理由
高速バスのキャンセル料が安いのは、もともと「乗合バス」として運行されてきた歴史があるためです。標準運送約款というルールにより、払戻し手数料は100円以内と決められていました。また、利用者の利便性を重視し、気軽に使える交通手段として発展してきたため、キャンセル料が低いままになっていたのです。

バス会社や社会の対応
キャンセル料の見直し
「相席ブロック」対策として、バス会社はキャンセル料を引き上げる動きを見せています。西日本鉄道の「はかた号」では、2024年12月からキャンセル料を段階的に大幅アップし、直前キャンセルには運賃の50%がかかるようになりました。他のバス会社でも同じような見直しが進んでいます。
ルールとマナーのバランス
SNSでは「性善説(みんなが善意で行動するという考え方)だけでは限界」という意見もあります。ルールを守らない人が増えると、全体のサービスが厳しくなるのは残念なことです。
他の交通機関との違い
新幹線や飛行機では、キャンセル料が高めに設定されているため、「相席ブロック」のような問題はほとんど起きていません。バスだけが特別にキャンセルが簡単だったことが、今回の問題の背景にあります。
まとめ
- 「相席ブロック」は高速バスの予約システムを悪用した迷惑行為
- キャンセル料の安さやウェブ予約の普及が問題の背景
- バス会社はキャンセル料の引き上げやルールの見直しを進めている
- ルールやマナーを守らないと、全体のサービスが厳しくなってしまう
- 他の交通機関では、キャンセル料が高いため同じ問題は起きにくい
サービスのルールや料金は、みんなが気持ちよく利用できるように工夫されています。しかし、一部の人がルールのすき間を悪用すると、全体の仕組みが変わり、利用者全員に影響が出ます。ビジネスの現場では「機会損失」や「モラルハザード」という言葉が使われます。これらは社会全体の信頼を守るために重要な考え方です。
みなさんも、身近なサービスのルールがなぜあるのか、どんな工夫がされているのかを調べてみましょう。自分がサービスを利用するとき、どんな行動がみんなのためになるか、一度考えてみてください。