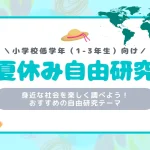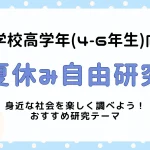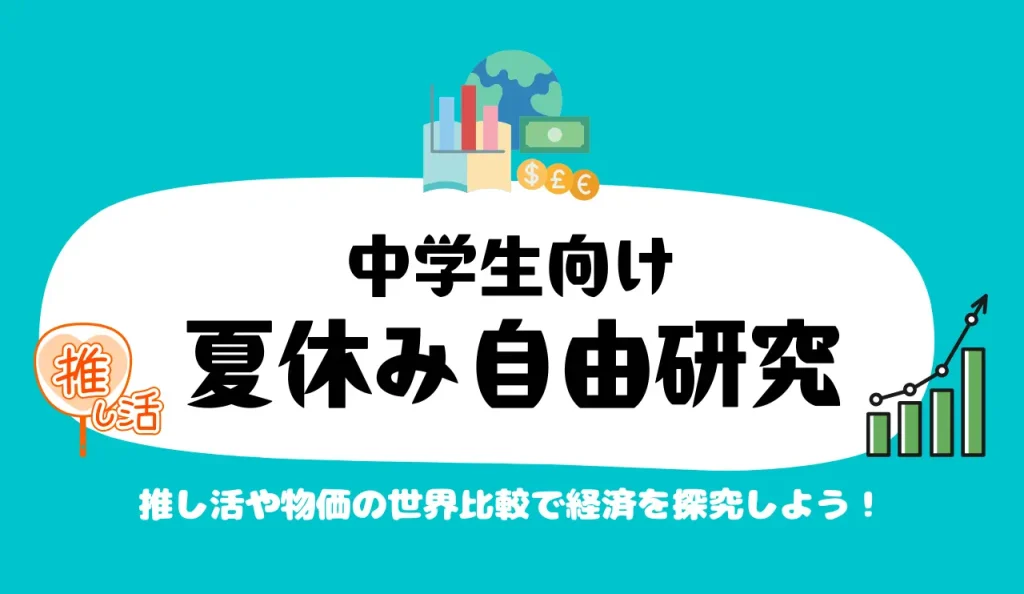
「世界では同じものなのに、なぜ国によって値段がこんなに違うの?」「好きなアイドルを応援する“推し活”が、どうしてニュースになるくらいの経済効果を生むの?」
ふだん何気なく目にする物価や“推し活”の裏側には、知れば知るほど面白い「経済のひみつ」がたくさん隠れています。
ただ調べるだけじゃ物足りない、もっと深く、本当の理由まで自分の頭で探りたくなるはずです。
物価と生活の関係分析

研究の目的
物価は毎日の暮らしに直結しています。最近のインフレ(物価上昇)は、家庭や地域にどんな影響を与えているのでしょうか。実際のデータや身近な声を集めて、経済の動きを自分で読み解く力を身につけます。
なにがわかる?
- 物価上昇が家計や地域にどんな影響を与えているか、具体的に理解できます。
- データやインタビューをもとに、社会全体の動きと自分の生活の関係を考えられるようになります。
調べ方のステップ
- 物価データを調べる
総務省やニュースサイトで「消費者物価指数(CPI)」や食品・電気代などの値上がりデータを集めます。
例えば、2025年5月の日本のインフレ率は3.5%で、特に食料品や電気代の値上がりが目立っています。 - 家庭や地域の声を集める
家族や地域の人に「最近、物の値段が上がったと感じるものは?」「生活で工夫していることは?」などインタビューします。 - データと声をまとめて分析する
どの品目がどれだけ上がったか、生活にどんな影響があるかを表やグラフでまとめます。例えば「米の価格が前年同月比で約95%も上昇した」というデータを使い、家庭の食卓への影響を考察します。 - 発見や疑問をまとめる
物価上昇の原因(円安、輸入コスト増、エネルギー価格上昇など)や、家計の工夫(まとめ買い、節電、安売り活用など)を自分の言葉で整理しましょう。
研究で参考になるサイト
保護者のサポート
- 家計簿やレシートを一緒に見ながら、値上がりした商品を探すお手伝いをしてあげましょう。
- インタビューの相手や質問内容を一緒に考え、まとめ方のアドバイスをしてあげてください。
「推し活」経済の研究

研究の目的
アイドルやキャラクターなど、好きなものを応援する「推し活」は、今や大きな経済現象です。
自分や友達の“推し活”が、どんなふうに社会や経済に影響しているのかを調べてみましょう。
なにがわかる?
- 推し活による消費行動や、関連グッズ・イベントがどれだけ経済を動かしているかを実感できます。
- 地域活性化や新しいビジネスのヒントも発見できます。
調べ方のステップ
- 家族でルールを決める
「今日はお金を使わない日」と決め、どんなことならOKか話し合います。
例:家にある食材だけでご飯を作る、外遊びはOK、交通費は使わないなど。 - 1日の計画を立てる
朝から夜までの過ごし方を考えます。おやつや遊びも工夫してみましょう。 - 実際にチャレンジしてみる
困ったことや工夫したことをノートに記録します。
例:「冷蔵庫の残り物でカレーを作った」「友達と公園で遊んだ」など。 - 振り返り・まとめ
1日終わったら、どんな工夫ができたか、何が大変だったか、どんな発見があったかをまとめます。
研究で参考になるサイト
保護者のサポート
- インタビューの相手や質問内容を一緒に考え、データの探し方をアドバイスしてあげましょう。
- イベントやグッズ購入の記録を一緒にまとめ、経済効果を考える視点をサポートしてください。
「物価の違い」を世界と比較

研究の目的
同じ商品でも国によって値段が大きく違います。世界の物価を比べることで、日本の立ち位置や為替、経済力の違いを学ぶことができます。
なにがわかる?
- 世界の物価水準や為替の影響、日本の経済力について実感できます。
- 国際的な視点で経済を考える力が身につきます。
調べ方のステップ
- 比較する商品を決める
ビッグマック、コカ・コーラ、映画チケットなど、世界共通の商品を選びます。 - 各国の値段を調べる
例えば2025年1月時点のビッグマック価格は、日本480円、アメリカ5.79ドル(約894円)、スイス1,234円などです。 - ビッグマック指数を計算・比較する
ビッグマック指数は「各国のビッグマック価格/米国の価格/為替レート-1」で算出します。日本は世界54カ国中44位で、物価は決して高い国ではありません。 - まとめと考察
なぜ値段が違うのか(為替、経済力、原材料費など)、日本の特徴や課題を自分の言葉でまとめます。
研究で参考になるサイト
保護者のサポート
- 商品選びやデータ集めをサポートし、計算方法や表の作り方を一緒に考えてあげてください。
- 世界地図を使って、各国の物価を視覚的にまとめるサポートをしてみてください。
さいごに
- 経済のテーマは一見むずかしく感じるかもしれませんが、「物価」「推し活」「世界と日本のちがい」など、実は私たちの暮らしに深く関わっています。
- 数字やデータ、身近な体験、インタビューなどを組み合わせて調べてみると、社会のしくみやお金の流れがぐっとわかりやすくなります。
- 表やグラフ、地図を使ってまとめることで、調査した内容の説得力が増し、発表やポスター作りにも役立ちます。
- 物価の変化から家庭や地域の課題に気づいたり、推し活から消費活動と地域経済のつながりを考えたり、世界との値段の差から日本の立場や経済力を実感することができます。
- 「どうしてこうなるの?」「もしこうだったらどうなる?」という問いを持ち、自分で考えた視点で自由研究に取り組むことが、これからの学びにもつながります。
経済とは、お金の話だけではなく、「人の行動」や「社会のつながり」を理解するためのカギです。この夏、自分の視点で社会を見る力を育てる自由研究に、ぜひチャレンジしてみてください。