アメリカで就職難、日本は売り手市場―AIが変える新卒採用
2025年、アメリカでは大卒の若者を中心に「就職氷河期」と呼ばれる厳しい状況が広がっています。特にIT企業を志望する学生でさえ、希望する職に就くことが難しくなっています。
その一因として「生成AI(人工知能)」の活用拡大があります。AIがプログラミングや事務作業を代替することで、新人採用が抑えられているのです。一方で、日本では状況が異なり、企業が人材確保に苦戦する「売り手市場」が続いています。
アメリカと日本の就職事情の違いや、過去の日本の就職氷河期の背景を見てみましょう。
アメリカ―AIが生む就職氷河期
アメリカでは、IT大手を中心に新卒採用が大幅に減少しています。2025年春には、コンピュータサイエンスを学んだ新卒者でも就職先が見つからず、アルバイトに頼らざるを得ない事例が報じられました。アメリカの若年失業率は全体より高く、22~27歳の大卒者で5.8%、コンピュータサイエンス専攻に限ると6.1%に達しています。哲学専攻の3.2%を上回る結果は、多くの人に衝撃を与えました。
背景には生成AIの導入があり、企業はプログラム作成や資料作成などをAIに任せ、人件費削減を進めています。実際に米国IT企業の新卒採用は前年比で25%減少しました。
日本―売り手市場で高水準の内定率
日本では新卒採用の状況が好調です。2025年卒大学生の就職内定率は91.7%と高く、求人倍率も1.75倍を記録しています。企業は人材確保のために、早期選考やインターンシップの拡充を進めています。
また、日本の学生もAIを積極的に活用しており、就職活動でAIを利用した経験がある学生は50%を超えています。エントリーシートの作成や面接練習に生成AIを取り入れる動きが広がっています。
識者・SNSの声
厚生労働省や総務省の調査では、「AIは人手不足を補い、生産性を高める手段」と評価されています。その一方で「AIと共存するためには応用力や実務経験が重要」という指摘も増えています。
SNS上では「AIに仕事を奪われる不安」と「AIで業務が効率化された安心感」が混在し、意見が分かれています。
過去の日本の就職氷河期―なぜ起きた?
日本の就職氷河期は1993年から2005年頃まで続きました。その背景には1990年のバブル崩壊後の景気後退がありました。求人倍率は1991年の2.86倍から1999年には0.48倍にまで低下しました。
さらに、アジア通貨危機や消費税の引き上げ、不良債権問題、金融機関の破綻など複数の要因が重なりました。労働者派遣法の改正で非正規雇用が増えたことも影響し、正社員として安定したキャリアを築けない世代が多く生まれました。
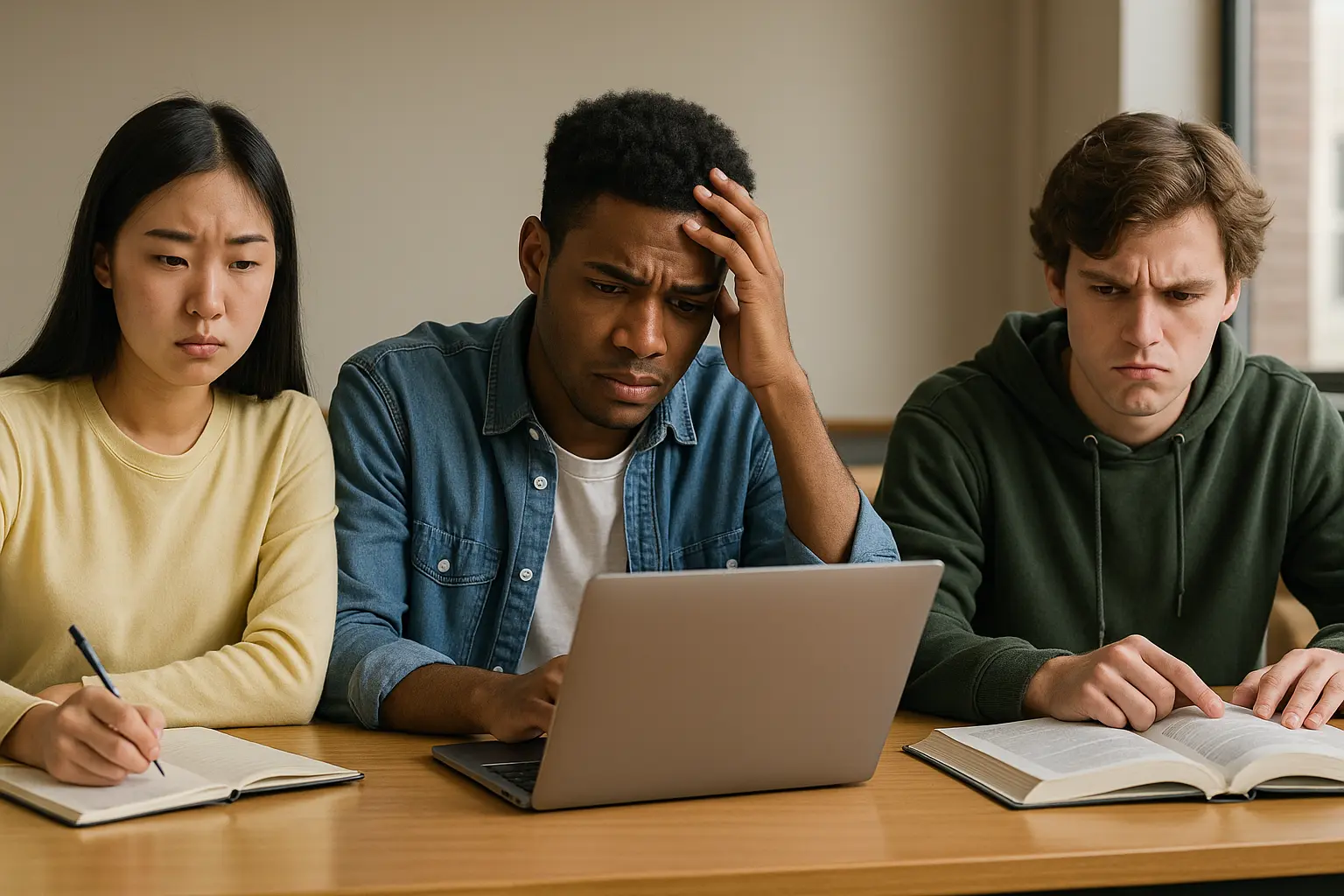
まとめ
- 米国では生成AIの導入が新卒就職難の要因になっている
- IT系専攻でも失業率が高く、新卒採用は前年比25%減少
- 日本は就職内定率が91.7%、求人倍率1.75倍と好調
- 日本でもAI活用が広がり、学生も企業も利用が進んでいる
- 識者はAIの生産性向上を評価しつつ、応用力の重要性を指摘
- 日本の就職氷河期はバブル崩壊や制度要因が原因
- 非正規雇用の拡大が社会問題を生んだ
米国と日本の就職状況を比較すると、AI時代に必要なのは「AIをどう使うか」という力だとわかります。今後はAIに代替されにくい発想力や実践経験が大切です。経済や雇用のニュースを日常的にチェックし、どのようなスキルが将来役立つのかを考えてみてください。
例えば「AIを使って効率化する力」と「人にしかできない判断や工夫」を組み合わせることが、これからのキャリア形成に役立ちます。親子で「自分ならどんな働き方を選ぶか」を話し合うこともおすすめです。





