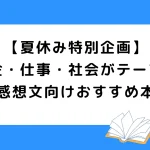TikTokで10歳が460万円投げ銭!未成年高額課金と返金訴訟
TikTokで10歳男児「投げ銭」460万円課金 取り消し求め運営会社提訴へ - 産経ニュース
動画投稿アプリのTikTok(ティックトック)で当時10歳の小学生男児が行った課金行為は無効だとして、男児側がアプリの運営会社のバイトダンス(東京)と課金プラ…
スマートフォンでお金を使うことは、今や子どもたちにも身近な出来事です。しかし最近、TikTokで10歳の男の子が約460万円もの「投げ銭」をしてしまった事件が話題になりました。家族が運営会社を訴えるまでに発展したこのケースは、日本だけでなく世界でも増えています。
なぜこのような高額課金が起きるのか、どんな仕組みで防げるのか――お金と契約のルールを見直すきっかけにしましょう。
TikTokで起きた高額課金
大阪府の10歳の男の子が兄のスマホを使ってTikTokで「投げ銭」を行い、約460万円を課金しました。クレジットカードが登録されていたため、何度も購入できてしまったのです。家族が気づいたのは、カード明細を見たときでした。消費生活センターに相談し、Appleからは約90万円が返金されましたが、TikTokの運営会社は返金に応じませんでした。
男の子は「お金を使っている」という意識がなく、成績次第で課金を許される家庭のルールも影響したと考えられています。
「投げ銭」の仕組みと課題
TikTokでは、配信者に応援の気持ちとしてギフトを送ることができます。その価格は2円から7万円以上まであり、230種類を超えるアイテムが存在します。複数回購入すれば、すぐに高額になります。課金の上限が明確に設定されていないため、クレジットカードと連携していると歯止めがかかりません。
日本の法律:未成年者取消権とは
日本では「未成年者取消権」により、親の同意なしに行った契約を取り消すことができます。スマホ課金もこれに該当する場合があります。ただし、年齢を偽った場合などは取り消しが認められないこともあります。消費生活センターや弁護士を通して返金交渉を行う例も増えています。
世界の事例:各国の対応
アメリカではゲーム「フォートナイト」を運営するEpic Gamesが、未成年の無断課金問題で約360億円の返金と400億円の罰金を命じられました。Appleでも、保護者の許可なしで課金した子どもたちへの集団返金訴訟が起きています。
中国では裁判で未成年の課金が「取り消し」認められた例があり、韓国も未成年保護のための法整備を進めています。
対策:家庭と企業の取り組み
課金トラブルの背景には、家庭でのルール不足や企業の年齢確認の甘さがあります。日本の消費生活センターは、返金交渉や相談窓口を設けて未成年の被害を減らそうとしています。家庭でも、利用時間や課金上限を設定し、子どもと一緒にルールを話し合うことが大切です。

まとめ
- TikTokなどのアプリでは、投げ銭による高額課金が起こることがある
- 日本では「未成年者取消権」で返金が認められるケースもある
- アメリカや中国などでも、同様の返金訴訟や制度が存在
- 家庭と企業が協力して年齢確認や利用管理を強化することが重要
スマホやアプリでお金を使うとき、「契約」というルールが関係しています。親の同意が必要な理由は、子どもを守るためです。もしトラブルが起きたら、あきらめずに家族や消費生活センターに相談しましょう。世界でも同じ問題が起きており、「お金を使う力」はこれからの時代に欠かせません。
これをきっかけに、金融やビジネスの仕組みを学び、正しく判断できる力を身につけてみませんか?