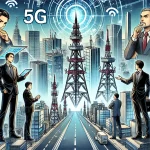「値上げしない」楽天モバイルは“アンフェア”か?携帯料金とインフラの関係
楽天モバイルの値上げしない発言に、「アンフェアだ」とソフトバンク宮川社長 一体なぜ? - ITmedia Mobile
ソフトバンクは11月5日、「2026年3月期 第2四半期 決算説明会」を開催。宮川潤一社長が登壇。料金プランに関して「アンフェアじゃないか」などとコメントした。
2025年、携帯電話会社の料金改定が相次ぐ中で、楽天モバイルは「値上げしない」と発表しています。一方、ソフトバンクの宮川潤一社長はこれを「アンフェア(不公平)」と批判しました。背景には、携帯会社が全国に通信インフラ(基地局)をどの程度自前で持ち、どれだけ費用を負担しているかという大きな違いがあります。
料金の裏側にあるインフラ投資・収益構造・家計への影響を考えてみましょう。
なぜ「アンフェア」と言われたのか:通信インフラの違い
大手3社(NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク)は、人口の少ない地域も含めて全国に基地局を設置し続けています。これは電波法や総務省ガイドラインに基づくものです。
一方、楽天モバイルは自社網の整備を進めつつ、地方など一部ではKDDI回線にローミング(回線を借りる形)で接続しています。自前の設備投資が完全に同等ではない点が、ソフトバンク社長の「費用負担が公平でない」とする発言の根拠です。
ただし、楽天側も基地局を継続的に増設しており、ローミング依存を減らす方向で投資を続けています。
値上げはなぜ似た時期に起きる?
2025年に各社が料金を引き上げたり、新料金プランへ移行したりした動きは共通しています。これを「値上げの額や時期を話し合って決めているのでは?」という疑いがでることもあります。しかし、公正取引委員会は「価格協定の事実は確認していない」としています。
値上げの主な要因は次の通りです。
- 基地局や海底ケーブルなどの設備投資費の上昇
- 人件費の上昇
- データ利用量の増加に伴う運用コスト増
つまり、「話し合って決めた」ではなく、「同じ市場環境で同じ方向に動いた」ことが背景にあります。
利益率から見える、大手と楽天のビジネス構造の違い
大手3社の営業利益率はおおむね20%前後で安定しています。契約者数が多く、長期的に設備投資を回収できる仕組みがあるためです。
一方、楽天モバイルは2025年夏の決算で「四半期ベースでの営業黒字化」を発表しましたが、年間ベースでは赤字が続いています。
- 大手:大規模な既存インフラ → 安定収益
- 楽天:参入が遅く投資負担が大きい → 収益化まで時間が必要
この違いが、料金戦略に反映されています。

家計への影響:月数百円の差でも大きい
4人家族が1人あたり月6,000円の携帯料金を払うと、年間で約28万8,000円。 もし1人あたり月400円値上げがあれば、年間で約2万円の負担増になります。
しかし、料金が安くても通信エリアが十分でない場合、地方でつながりにくいなどの不便が生じることもあります。「価格」と「つながりやすさ」はトレードオフになることがあります。
まとめ
- 楽天モバイルが「値上げしない」と宣言 → ソフトバンク社長はインフラ負担の違いを理由に「アンフェア」と指摘
- 大手3社は全国で基地局整備を継続
- 大手は利益率が高い、楽天は黒字化に向け改善中
- 料金は家計に影響が大きいため、選択は重要
- 通信品質と価格のバランスをどう考えるかがポイント
携帯料金は「毎月当たり前に払っているもの」ですが、その背景には企業の投資額、地域のインフラ整備、料金戦略など多くの要素があります。使う側にとって大切なのは、「自分にとって本当に必要な品質やサービスは何か」を考えることです。ぜひ、家族で次の点について話してみてください。
- 住んでいる地域で「つながりやすさ」はどれくらい重要?
- 動画・SNS・通話など、何にどれくらい通信を使っている?
- 「安さ」だけで選ぶと、どんな点が困る可能性がある?
- 新しいプランが出たとき、何を比較すればよい?
携帯料金の仕組みを知ることは、お金の使い方を考える力につながります。