なぜ留学生にも支援?博士課程の奨学金と財源のヒミツ
「博士課程ってお金がかかるって聞いたけど、本当に大丈夫?」「どうして日本は留学生も支援するの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は、日本には博士課程の学生を支える制度があり、年間290万円もの支援を受けられることもあります。 ですが最近、「財源はどうなっているの?」「自国民をもっと支援すべきでは?」という声も増えてきました。
博士課程の支援制度の仕組みや、留学生支援の理由、背景にある考え方について見てみましょう。
博士課程の経済支援とは?
なぜ支援が必要なの?
博士課程では、研究に多くの時間を費やすため、アルバイトをする余裕があまりありません。 それでも学費や生活費はかかるため、経済的な負担が大きくなります。 そのため、国や大学が支援制度を設け、学生が安心して研究に集中できる環境を整えています。
SPRING制度とは?
文部科学省の「次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)」は、博士課程の学生に年間最大290万円を支給する制度です。
この支援金は生活費や研究費に使うことができ、3~4年間受け取ることが可能です。 この制度の効果により、2024年度の博士課程進学者数は前年比5%増の1万5744人となりました。

支援の財源はどこから来るの?
博士課程の支援金は、主に国の予算から出されています。 文部科学省が予算を確保し、科学技術振興機構(JST)などを通じて大学に配分しています。 また、大学独自の取り組みや、研究アシスタント(RA)やティーチングアシスタント(TA)としての雇用による支援も含まれます。
規模を広げるには、毎年100億円以上の追加予算が必要とされています。
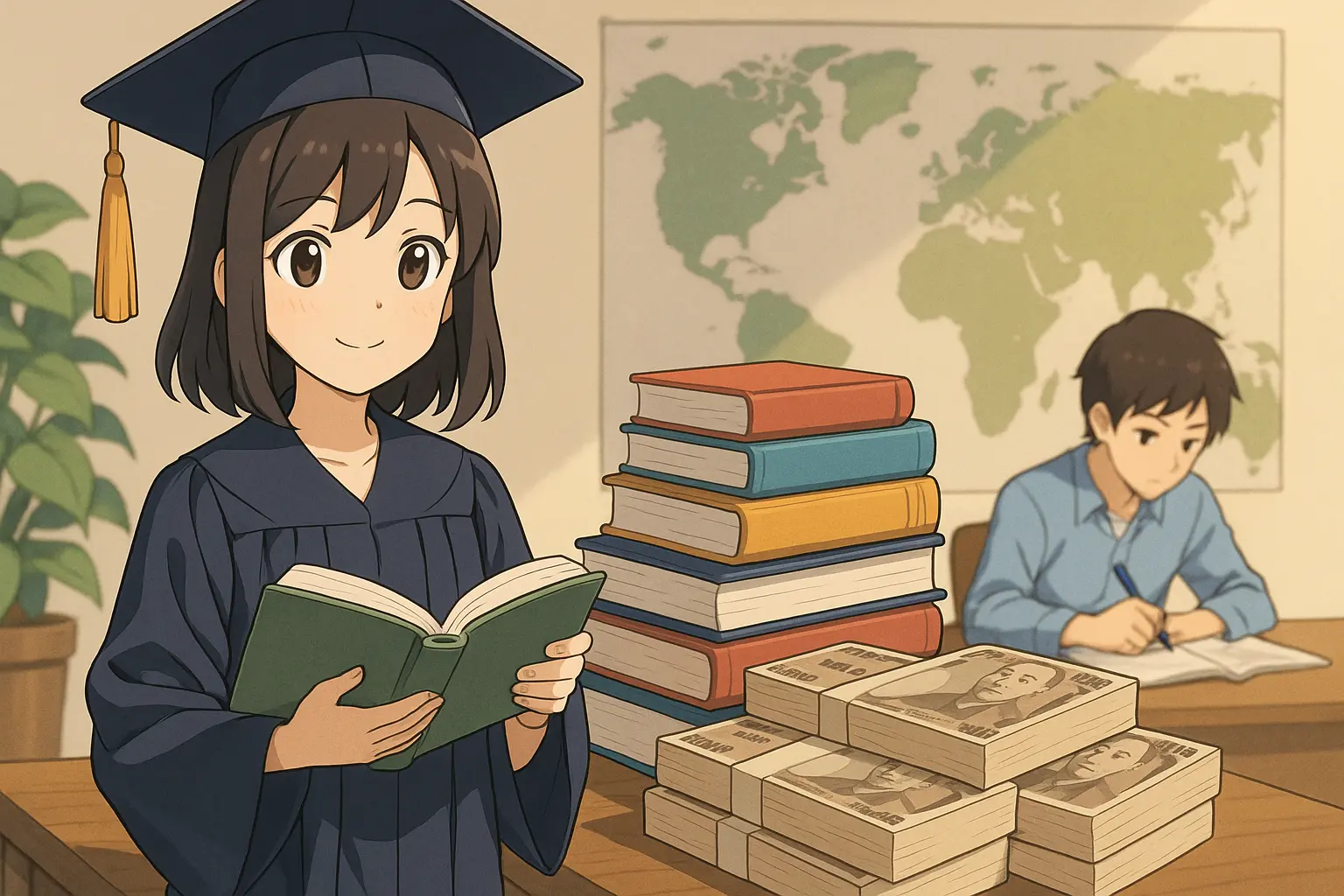
なぜ日本は留学生も支援するの?
国際化の推進と交流の広がり
日本が留学生を支援する大きな理由のひとつは、大学や社会の国際化を進めるためです。 世界中から優秀な学生を受け入れることで、科学や産業の発展につながります。 また、異文化との交流を通じて、日本人学生の視野も広がります。
経済への好影響
留学生が日本で学び、生活することにより、学費や生活費が地域経済に貢献します。 さらに、卒業後に日本企業で働けば、企業の国際競争力向上にも役立ちます。 地方大学では、人口減少対策や地域活性化の面でもプラスになります。
相互主義とSDGsの理念
日本人学生も海外で支援を受けているように、留学生への支援も「おたがいさま」という相互主義に基づいています。 この取り組みは、国連のSDGs「質の高い教育をみんなに」という目標にもつながっています。
「日本人を優先すべきでは?」という意見にどう答える?
- 留学生支援は国際化の一部であり、日本の発展に貢献しています。
- 経済効果や地域活性化を通じて、社会全体にメリットがあります。
- 日本人も海外で同様の支援を受けており、対等な関係に基づいています。
- SDGsの考え方に沿い、世界全体で教育の機会を広げる取り組みです。
最近、博士課程の支援制度が見直されつつあります。 今後は「日本人を基本」としながらも、優秀な留学生を引き続き支援対象に含める方向で調整が進められています。 支援の拡充により、博士課程への進学者が増加し、さまざまなバックグラウンドを持つ人材が研究現場で活躍しています。
まとめ
- 博士課程の支援は、研究に集中できる環境づくりのために重要
- 財源は国の予算や大学独自の取り組みから
- 留学生支援は国際化や経済への効果、SDGsの実現に役立つ
- 「日本人を優先すべき」という意見には、相互主義や国際的な利益が回答
- 支援の見直しと拡充により、日本の未来を担う人材が育つ
博士課程や留学生支援について知ることは、社会や経済の仕組みを理解する第一歩です。 将来、「研究者になりたい」「世界とつながる仕事がしたい」と思ったとき、どんな制度があるのかを自分で調べてみてください。
ニュースや社会の変化にも目を向けることで、自分の進路や夢にもヒントが見つかるはずです。

【無料オンラインイベント】8/25(日)「第3回 クイズで学ぶ!お金と社会のつながり」
<詳細・お申込みはこちら>






