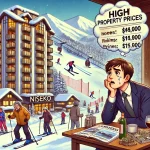お寺の入山料は現金のみ?山形・山寺の支払い問題と日本のキャッシュレス事情
お寺や神社を訪れるとき、現金を持っていきますか?おさいせんを入れたり、御朱印帳を買ったりするためにはお金が必要ですよね。
近年、日本ではキャッシュレス決済の普及が進み、多くの店舗や観光施設でクレジットカードや電子マネーが利用可能になっています。しかし、すべての場所がキャッシュレスに対応しているわけではありません。
例えば、山形県の観光地「山寺(立石寺)」では、訪日外国人観光客がクレジットカード決済をした後、「現金で返金してほしい」と頼むケースが増えています。この問題は単なる支払い方法の違いではなく、日本の伝統とキャッシュレス化のバランスをどう取るかという課題にもつながります。
山寺の現金問題とは?
現金のみ対応の影響
山寺(立石寺)では、訪日外国人観光客が土産店でクレジットカード払いをした後、「現金で返金してほしい」と求めるケースが増加しています。
これは、山寺の入山料(300円)が現金のみ対応であるため、多くの外国人が事前に現金を用意していないことが原因です。
政府はインバウンド観光促進の一環としてキャッシュレス化を推進していますが、地方の観光地では対応が進んでいないため、このような問題が発生しています。
山寺の立場と課題
山寺側はキャッシュレス決済を導入する予定はなく、伝統的な「お布施」の文化を守る方針を取っています。
- お布施は信仰の一環として現金でのやり取りが基本
- デジタル決済に馴染まないという考え方が根強い
- 設備投資や手数料負担の問題もあり、導入のハードルが高い
しかし、キャッシュレス化が進む現代において、観光客の利便性とのバランスをどのように取るかが課題となっています。
他の観光地での対応策
1. キャッシュレス決済の導入
京都や奈良では、一部の神社仏閣で以下のようなキャッシュレス決済が導入されています。
- QRコード決済(例:PayPay、LINE Pay など)
- 電子マネー決済(例:Suica、PASMO など)
しかし、依然として現金のみ対応の場所も多く、完全なキャッシュレス化には至っていません。
一方で、ヨーロッパやアメリカの観光地では、ほぼすべての施設がキャッシュレス対応を進めています。
フランスのルーブル美術館
・公式ウェブサイトでのチケット購入や館内ショップではキャッシュレス決済が一般的
・一部の窓口では現金支払いも可能
この違いを理解することで、日本の対応の特徴や課題がより明確になります。
2. 多言語対応の強化
観光案内板やパンフレットを多言語化し、日本独自の文化や参拝マナーを事前に伝える取り組みが進められています。これにより、訪日客がスムーズに支払いを済ませられるようになります。
3. 文化体験プログラムの導入
茶道体験や写経体験など、日本文化をより深く知ることができるプログラムを提供し、外国人観光客との交流を促進しています。
お寺の税制と収益活動
「お寺は税金を払っているの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
基本的に、宗教活動による収入(お布施やお賽銭)は非課税ですが、商業活動(宿坊運営や土産販売、飲食サービスなど)には課税されます。
この仕組みにより、宗教法人が行う経済活動の一部は一般企業と同様の税負担を求められています。この税制は、文化財の維持や伝統継承を支えるために設けられています。

まとめ
- 山寺では訪日客による現金問題が発生している
- 日本と海外ではキャッシュレス事情が異なる
- 山寺側は伝統文化を守る方針でキャッシュレス化を導入していない
- 他の観光地ではキャッシュレス化や多言語対応などが進んでいる
- お寺の税金は、宗教活動部分は非課税だが、営利事業には課税される
みなさんは、この問題についてどう考えますか?もし海外の観光地で「現金のみ対応」だったら、どのように対処するでしょうか?また、日本の伝統文化を大切にしつつ、外国人観光客が困らないようにするためにどんな工夫ができるでしょうか?
お寺が入山料の支払い方法を増やすための工夫、観光客が事前に現金を用意できる仕組みなど、「文化」と「経済」が交わる場所には、多くの学びがあります。
この問題について、あなたならどのような解決策を提案しますか?
例えば、現金のみの観光地でスムーズに支払うための工夫や、外国人観光客向けの新しい仕組みを考えてみましょう。

【無料オンラインイベント】8/25(日)「第3回 クイズで学ぶ!お金と社会のつながり」
<詳細・お申込みはこちら>