NHKが400億円の赤字に!受信料はどうなる?ネット配信も課金スタート
〈NHK・400億円の赤字〉「受信料支払いを拒否したら2倍」に続く徴収施策…狙いは「タワマン住民」と「テレビを持たない若年層」 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け
3月にNHKの2025年度予算が衆議院総務委員会で承認された。2023年10月の受信料1割引き下げの影響もあり、2025年度は400億円もの赤字が発生する見込みだ。強気の料金引き下げを行なったNHKだが、予算ベースでは3年連続の赤字となる。NHKの受信料の推計世帯支払率はおよそ8割で、高止まりの状態が続いていたが、赤字が続いたことで徴収を強化する未来も見えてくる。
「最近ニュースでNHKが赤字だって聞いたけど、どうして?」「テレビはあまり見ないけど、受信料って払わないといけないの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?
NHK(日本放送協会)は、日本の公共放送として私たちにニュースや教育番組を届ける存在です。しかし、現在NHKは大きな赤字に直面しており、2025年度には約400億円の赤字が見込まれています。なぜこのような事態になっているのでしょうか?
NHKの赤字問題と受信料制度の背景、そして今後の公共放送のあり方について考えてみましょう。
NHKとはどんな組織?〜公共放送と株式会社のちがい〜
公共放送の役割とは
NHKは「公共放送」として、特定の企業や個人の利益ではなく、社会全体のために情報を届ける使命を持っています。災害時の緊急報道や教育番組、ドキュメンタリーなど、利益重視では作りづらい番組を放送するため、視聴者から集めた受信料によって運営されています。
株式会社とのちがい
株式会社は利益を追求し、株主の利益を最大化することが目的です。一方、NHKは利益ではなく公共の福祉を目的としています。そのため、経営計画も国民や国会のチェックを受けながら決められており、必要であれば赤字の計画も許容されます。
なぜNHKは赤字なの?
受信料の値下げ
2023年10月、NHKは国民への還元として受信料を1割引き下げました。視聴者にとっては歓迎されることでしたが、NHKにとっては大きな減収となり、赤字の原因となりました。
テレビ離れと契約数の減少
若者を中心にテレビを見ない人が増え、スマートフォンやパソコンで動画を見ることが主流になっています。その結果、テレビを持たない世帯も増え、NHKとの受信契約件数が大幅に減少しています。
受信料を払わない世帯の存在
テレビを所有していても、正当な理由なく受信料を払わない世帯も一定数あります。これもNHKの収入減に大きく影響しています。
赤字が続くとどうなる?
- 番組の質が下がる可能性(報道やドキュメンタリーの縮小)
- 将来的に受信料が値上げされる可能性
- サービスの見直しや縮小
- 公共放送の意義や受信料制度の見直しが議論される可能性
この問題は、視聴者である私たちにとっても無関係ではありません。
NHKの収入確保のための取り組み
受信料の徴収強化
2023年4月から「割増金制度」が始まりました。これは、受信契約を結ばない世帯に通常の2倍の受信料を請求できる制度です。実際に裁判で支払いが命じられたケースもあります。
タワーマンション対策
訪問員が入りにくい高層マンションでは、販売会社や管理組合と協力し、入居時に受信契約を促す仕組みを導入しています。
ネット配信利用者への課金
2025年10月からは、テレビを持っていなくてもNHKのネット配信を利用する契約者には、地上契約と同額(月1100円)の受信料が請求される予定です。これは、Netflixなどと同様に「使う人が払う」仕組みに近い制度です。
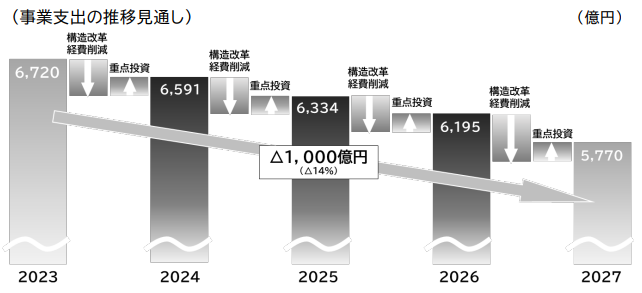
NHKの強みと課題
強み:信頼性の高い報道
災害時の緊急報道や、社会問題を掘り下げたドキュメンタリーなど、NHKの報道は正確で信頼性が高いと見なされていることが特長です。フェイクニュースが多い今だからこそ、信頼できる情報源としての役割は重要です。
課題:魅力あるコンテンツづくり
YouTubeやNetflixなどのサービスに慣れている視聴者に「NHKを選んでもらう」には、魅力ある番組を作り続けることが求められます。受信料を払ってでも見たいと思えるような価値あるコンテンツを届ける必要があります。

まとめ
- NHKの赤字は、受信料の値下げとテレビ離れが主な原因
- 赤字が続けば、番組の質や受信料制度に影響が出る可能性がある
- NHKは割増金制度やネット受信料で収入の確保を進めている
- 信頼性の高い報道という強みを活かし、今後も価値ある情報を届ける必要がある
- NHKは利益追求の株式会社とは異なり、公共の福祉を目的に運営されている
NHKの問題は、私たちの生活にも関係があります。たとえば道路や図書館など、利益を出さないけれど必要とされる公共サービスと似ています。社会にとって必要なサービスを、どうやって支え続けるのか。NHKの例を通して考えてみると、経済やビジネスの仕組みも見えてきます。
「公共放送って必要?」「受信料制度はこのままでいいの?」そんな問いかけをきっかけに、家族や友達と話してみたり、自分でも調べてみたりしてみましょう。それが、自分の未来と社会を考える第一歩になります。

【無料オンラインイベント】8/25(日)「第3回 クイズで学ぶ!お金と社会のつながり」
<詳細・お申込みはこちら>







