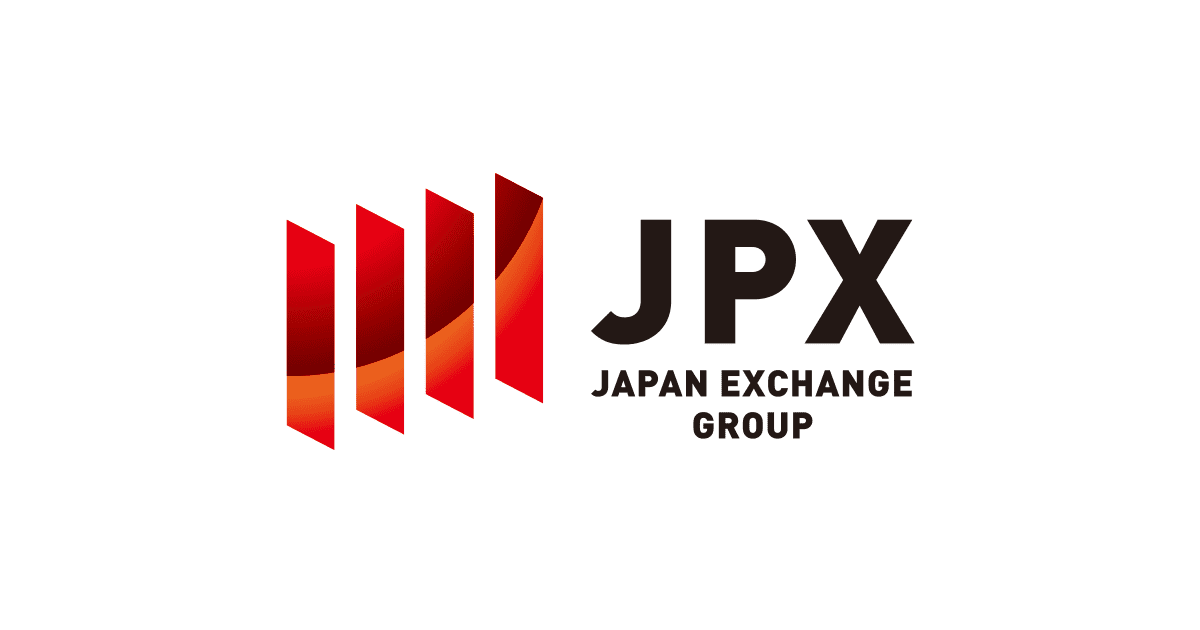東証グロース市場に“100億円ルール”登場?上場企業多すぎる問題の対策にも?
上場5年で時価総額100億円以上 東証、グロース市場改革案:時事ドットコム
東証は2日、新興企業向けグロース市場の上場維持基準について、「上場5年経過後から時価総額100億円以上」に厳格化する改革案を明らかにした。現行は「10年経過後から40億円以上」。機関投資家の出資対象となる規模の新興企業を増やし、日本経済の活性化につなげたい考えだ。
東京証券取引所(東証)は、新興企業向けの「グロース市場」で、上場から5年後に時価総額100億円以上を求める新しいルールを導入する方針だと報道されました。この変更は、企業の継続的な成長を後押しし、機関投資家の投資を促す狙いがあります。
しかし、日本には「上場企業が多すぎる」という問題や、上場をゴールにしてしまう「上場ゴール」という課題もあります。
東証の改革が日本の企業や経済にどのような影響を与えるかを考えてみましょう。
東証グロース市場の新ルールとは?
東証は、グロース市場に上場した企業に対して、上場後5年以内に時価総額100億円以上を達成することを求める方針である、と報道されました。このルールは2026年以降に適用される予定とのことです。目的は、将来有望な企業への投資を増やすことだと考えられます。
※ただし、日本取引所グループの発表によれば、この記事を書いている4/2 午後10時時点では、「グロース市場の機能発揮に向けた施策のひとつとして検討を行っておりますが、その内容についてはまだ決定をしてございません。」ということで、決定ではありません。
グロース市場の上場維持基準の見直しに関する一部報道について | 日本取引所グループ
グロース市場の上場維持基準の見直しに関する一部報道についてのページ。東京証券取引所、大阪取引所、東京商品取引所等を運営する日本取引所グループ(JPX)のサイトです。
なぜ新ルールが必要なの?
日本経済を元気にするためには、若い企業の成長が欠かせません。今回の改革により、企業は成長を意識しながら経営を進めるようになります。その結果、投資家の信頼を得て、経済全体にも良い影響が期待されています。
上場企業が多すぎる?
現在、日本には約3,900社の上場企業があります。これはアメリカよりも多い数で、世界的に見てもかなりの多さです。
どんな問題があるの?
上場企業の多くが小規模で、「小さい会社がたくさんある」状態です。このため、似たような会社同士での競争が激しくなり、利益を出すのが難しくなっています。また、一部の企業は市場との対話をあまりせず、現状維持を続けています。
東証の取り組み
東証は、企業の「数」ではなく「質」を重視するようになっています。経営に集中したい企業には、非上場に戻る道も尊重されるようになりました。市場再編によって、企業が自分に合った市場を選べるようにもなっています。
「上場ゴール」って何?
「上場ゴール」とは、会社が株式上場をあくまでお金集めの手段としか見ず、その後の成長を真剣に考えないことを指します。これは投資家からの信頼を失う原因になります。
どんな例があるの?
たとえば、上場してすぐに売上が落ちたり、商品が売れなくなったり、経営陣に問題が起きたりするケースがあります。これらが「上場ゴール」と言われる例です。
どう防ぐ?
企業は上場後も成長戦略をしっかりと立て、持続可能な経営を目指す必要があります。東証の改革は、こうした企業を応援する仕組みでもあります。
投資家目線で見る東証改革
今回の改革は、投資家にとっては歓迎すべき点が多いといえます。企業の質が高まり、成長意欲のある会社が目立つことで、投資判断がしやすくなるからです。また、ガバナンスや透明性の向上は、企業のリスクをより正確に評価する材料になります。
小規模企業への投資のリスクとは?
ただし、小規模企業への投資にはいくつかのリスクもあります。
- 業績の変動が大きい:市場や競合の影響を受けやすく、利益が安定しにくい傾向があります。
- 情報の少なさ:大企業に比べて公開されている情報が少なく、経営の透明性に欠ける場合があります。
- 経営の不安定さ:資金繰りや人材不足、ガバナンス面の課題が残っていることも多いです。
こうしたリスクを正しく理解し、複数企業に分散投資をするなどの工夫が、投資家に求められます。

東証の市場再編で見えた変化
2022年、東証は市場を「プライム」「スタンダード」「グロース」の3つに再編しました。これにより、投資家は企業の内容に合わせて投資先を選びやすくなりました。
なぜ再編が必要だったの?
これまでの市場では、企業の評価基準があいまいでした。新しい市場では、企業の透明性やガバナンス(企業の管理体制)など、質の高さが重視されています。
どんな影響があった?
企業は新たな基準に合わせて経営の透明性を高めています。その結果、海外の投資家も日本企業に注目するようになってきています。
企業の成長戦略の例
- 旭化成のM&A:旭化成はアメリカの技術企業を買収しました。これは企業の成長戦略の一部で、世界での競争力を高めるねらいがあります。
- 北浜キャピタルパートナーズ:再生可能エネルギー分野の子会社を経営陣に譲渡しました。環境ビジネスの強化を目指しています。
まとめ
- 東証はグロース市場で「時価総額100億円以上」という新基準を検討中
- 日本の上場企業数は非常に多く、小規模企業の乱立が課題
- 上場後に成長しない「上場ゴール」企業も問題視されている
- 東証の市場再編により、企業の質と透明性がより重視されるようになった
- 投資家にとっては、改革によって信頼できる企業を見極めやすくなる
もしあなたが会社を作るなら、上場をゴールにするのではなく、その先にどんな成長を目指したいですか?経済のニュースはむずかしく感じるかもしれませんが、自分の生活や将来にも関係があります。たとえば、どんな会社に投資してみたいか、どんな会社が社会をよくしてくれるのかを考えるきっかけにしてみましょう。

【無料オンラインイベント】8/25(日)「第3回 クイズで学ぶ!お金と社会のつながり」
<詳細・お申込みはこちら>